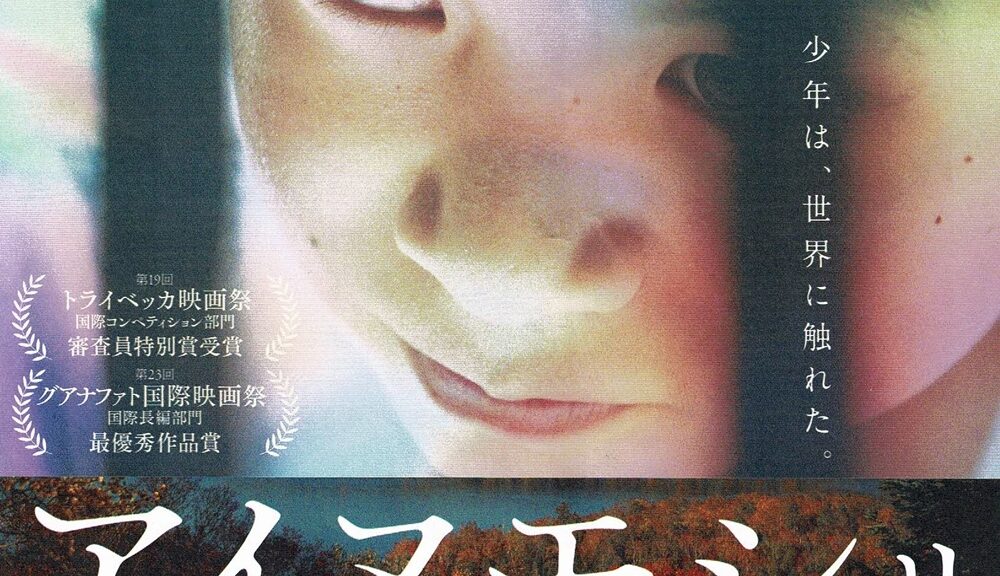1992年2月2日~9日
アメリカ合衆国:サンフランシスコ ロス アンゼルス ホノルル

グランドツアーは視察旅行の原点
アメリカには興味がないわけではないが訪問地の優先順位では欧州が先行している。都市観光の原点は17世紀に英国貴族の子弟が修学のためにおこなった海外旅行(グランドツアー。主に渡航先はイタリア)である。そんな貴族でも何でもないボクにもチャンスは巡ってきた。自治体職員の海外研修旅行というちょっと変わったグランドツアーであった。
釧路市役所から選抜された2名の職員がJTBが催行する海外先進自治体研修ツアーに参加する形であった。財政が逼迫して、おそらくこの年が海外研修の最後の年になったはずだ。
ボクは入所してちょうど20年目を迎え、役所生活の折り返し点だった。年齢も38歳。脂が乗った生意気な職員であった。
この研修の選抜にあたっては通常、部長クラスの推薦があって決められるのだが、ボクの場合は当時の職員課長がボクのことを気に入ってくれて推薦してくれた。
「塩、お前を海外研修に推薦したから」「ありがとうございます。ところでどちらですか?」「アメリカだ」「できればヨーロッパに行きたいですが…」「……」。
こんな感じだった。ボクたちは全国各地から集まった15名の参加者とともにアメリカに向かった。研修目的は、サンフランシスコ郊外のギルロイという街でニンニク(ガーリック)をテーマにした祭りの企画運営。ロサンゼルス郊外のサンタモニカ市で情報システムサービス。ホノルルのハワイ大学コミュニティカレッジで成人教育生涯教育の運用などであった。

研修後、ボクは約50ページに及ぶ記録報告書を作成した。参加者全員に配って「出張報告に使わしてもらうよ」とえらく感謝された記憶がある。全部は掲載できないので「研修後記」と「(職員課)研修担当へ」という2項目を抜粋し掲載する。
おおよそ30年前のボクの思考回路が今とあまり変わっていないことと、役所におけるボクの生意気ぶりが伝わる文章である。言いたいことは言わせてもらう。あまり忖度しない職員であった。
この後、ボクは港湾部に異動し、港祭りや港湾管理の仕事に従事した後、観光セクションに異動。観光振興に携わり阿寒湖温泉勤務で市役所生活を終える。この研修で見聞した祭り運営、フィッシャーマンズワーフ開発の様子やハワイの観光産業の振興策などは多かれ少なかれその後のボクの仕事の糧になったと思っている。
税金は無駄に使っていませんからぁ!
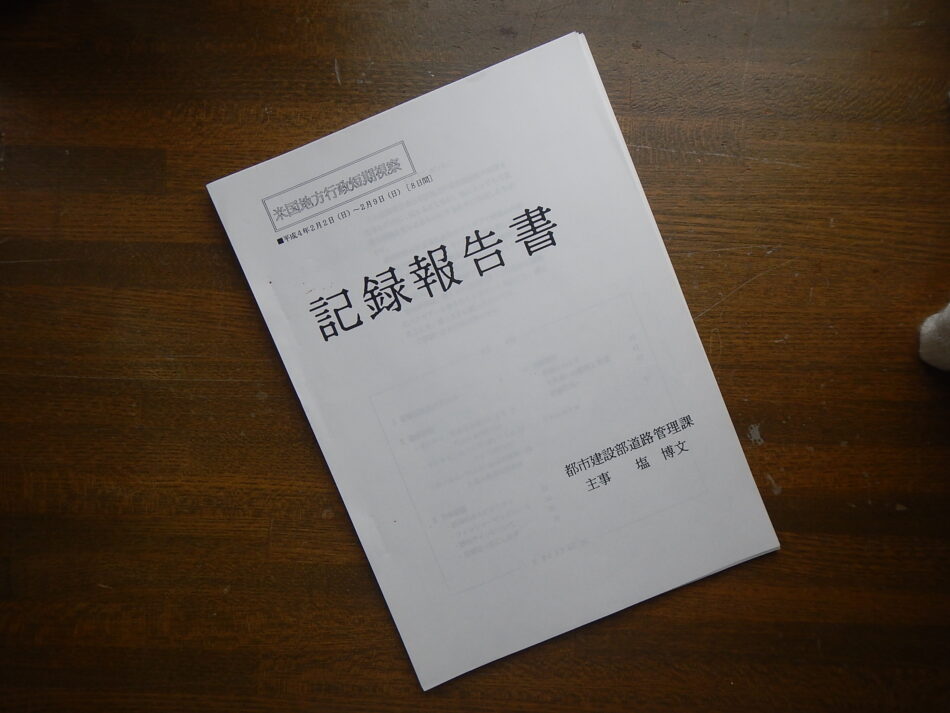
ちゃんと報告書を提出 
釧路からの参加者は最年少
研修後記
■研修を終えて
大雪、地震。飛行機は遅れる、電車は遅れる。集合時間にも遅れ、やっとこさのユナイテッド828便。二度あることは三度ある。すわ! サンフランシスコ大地震とおもいきや…。6泊8日の海外研修は順風満帆。天気に恵まれ、善意の人々に支えられ無事終了することが出来た。
視察研修は地域振興(ギルロイ、ガーリック祭)、公共情報ネットワーク(サンタモニカ、PENシステム)、成人教育生涯教育(ホノルル、カピオラニコミュニティカレッジ)といずれも釧路においてはタイムリーなテーマであり充実した視察であった。
国際化の時代といわれるが、テーマや表現力が類似していても、それを支える思想や思考には大きな違いがあるとおもう。近年の日本の経済成長により、「アメリカが手本の時代は終わった」とか「日本はアメリカを越えた」とか、威勢のいい声も聞こえるが、ここは謙虚に学ぶべき点は学ぶ姿勢が必要である。
ギルロイでは地域振興をとおし自立したボランテイア精神を知ることができた。サンタモニカでは民主主義の基盤となる、情報提供と民意の集積に対する積極的な自治体の姿勢を感じた。
ホノルルでは地域社会への貢献という建学精神を見事に反映した合理的な教育システムづくりに羨望の感すら抱いた。
これらはいずれもアメリカ社会の良質な部分として受け取ることは出来る。しかし一方で自由時間の間に見たサンフランシスコ、ロスアンゼルスのホームレスや冷徹なまでの棲み分け。どことなく暗かった街の人の表情や治安の悪さ(ボクは怖い目には合わなかったが…)。これも経済不況、人種問題、麻薬問題等々病める大国アメリカの一面なのであろう。これらは違う問題なのだろうか。実利主義に対する奉仕精神。競争原理が生み出す勝者と敗者。合理主義がもたらすシロクロのはっきりした社会等々。ボクには最大値と最少値の振幅が広い社会ではないかとおもわれた。
同時に移民の国として、来る者は拒まずの間口の広さ、懐の深さは島国に育ったボクには、やはり腐っても鯛(失礼!) であった。
個別の事例のなかに学ぶべき点や参考になる点もたくさんあった。結論的に言えば、平凡ではあるが釧路には釧路の良さがあって、その長所を踏まえた上で、検討モデルとして他国の社会を見つめる眼を持ちたいものだとおもった。
国際化の時代といわれるが、わけのわかんない政治家の暴言・失言(?) に振り回されるより、顔の見える地域間の国際交流の方が永い眼で見るとずっと実り多い相互理解を育むのではないかと実感した8日間であった。
■研修担当へ
短いような長いような8日間の研修でした。海外滞在期間中は五感がフルに活動するので濃度の高い時間を過ごすのだと実感しているところです。
この体験を市政に少しでも反映できるようにと、秋里君と共同で視察研修の採録を試みました。関係部局の職員及びテーマに関心のある方に少しは参考になるかとおもいます。
さて、せっかくの機会ですから勢いついでに、今回の研修をとおし海外研修システムそのものについての意見を述べさせていただきます。
1、今回の海外研修にボクは選ばれたのですが、本人の意志が反映しないこのような形より、希望の申告を前提とした選抜の方が民主的だとおもいます。今回の参加者の中でも、希望申告により来られた方もいました。他の研修とは違い、希望者全てが行けるわけでもないし、選ぶ上で難しい問題もあるのでしようが、やはり本人の主体性がどこかに確保されていることが必要だとおもいます。
2、今回は全額公費の研修でしたが、このような海外研修の機会拡大のために、費用の部分負担の研修もあってよいのではないでしょうか(全額公費で行った本人がいうのも図々しいとお思いでしょうが…)。たとえば、リフレッシュ休暇と海外研修の併用型(海外旅行の中に研修テーマがあるものに費用負担をおこなう)や姉妹都市交流と海外研修の併用型(姉妹都市を訪問する旅行プランには助成する。これは市民も対象にすべき)など、もっとバラエティーに富んだ研修システムがあってよいとおもいます。自己費用で海外に行き勉強してくる職員もいるのです。これらの人にも何らかのバックアップがあっても良いのではないでしようか。
3、非管理職員クラスの海外研修枠をひろげてほしいです。今回の参加者中、管理職でないのは釧路市の二人だけでした。「釧路は進んでいるなぁ」と嫌味でなく感心されました。ラムサール会議や釧路湿原の話にもあいまって釧路の国際交流にかける意欲を他の自治体の方にも感じてもらえたとおもいます。また、研修での体験を咀嚼し市政に反映するのは現場の職員ですし、研修成果をレポート等で広げる機会も縦割り組織を意識しなければならない管理職より自由に出来るのではないでしようか。
映画サークルなど民間での文化活動にも参加していて、市役所、さらには組合という組織においても役所内だけに通用する〈市役所文化〉みたいなものに対する不満が行間に顔を出す。それにしても約30年前の自分に会ったようで恥ずかしい。