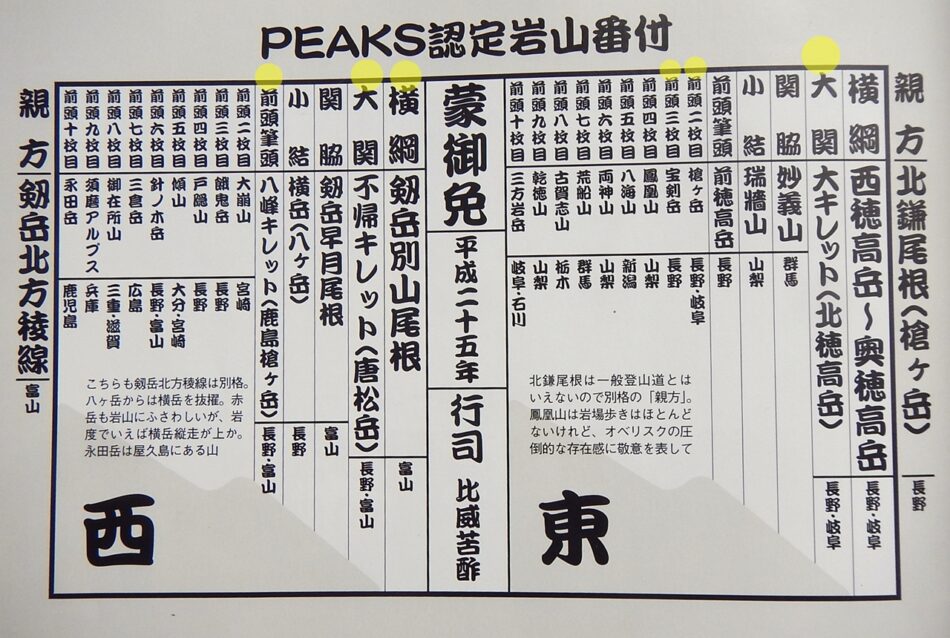2015年9月29日~10月5日
長野・善光寺、小布施 松本市 常念山脈 (燕岳~蝶が岳)

「インスタ映え」か、「フォトジェニック」か
旅先で写真をたくさん撮る。一週間前後の国内旅行で約3百カット。2週間弱の最も長かった海外旅行では1千5百カット以上撮ったこともある。
カメラを盗まれたとか、撮ったはずが写っていなかったとか、大きな失敗はないが、デジタルカメラの使い始めの頃、電池容量が分からず交換バッテリーも1個だけで充電器も持たずに出かけ、旅先で撮影不可状態になった。忘れもしないフィレンツェのリッカルディ宮で部屋全体にゴッツオリの「東方三博士の巡礼」が壁画になっているところでアウト。この絵がお気に入りの連れから叱られた。
撮影は興味のあるもの=撮りたいもの。小さな花から遠くの山まで。マクロ撮影から望遠までが守備範囲である。
旅先に持っていくカメラは、現在は4台の内のいずれかとスマホ。一番使用頻度が高いのは右端のニコンCOOLPIX。高校時代、写真部からの友人であるO君が退職祝いにプレゼントしてくれた。海外旅行から登山まで、とにかく軽量でいつでも取り出せ、どこでも撮影が可能な一台である。大体このカメラとスマホが旅の相棒である。重い一眼レフはご法度である。
右から2番目のキャノンPowerShotは自前のカメラ。主に仕事で野鳥や風景を撮る時や荷物に余裕のある時に使う。
一番大きなペンタックスはボクの写真部の先輩、Uさんの形見である。彼と一眼レフの使い方を忘れないように、たまに使う。

写真部の顧問はアマチュアカメラマンとして実績のある方で、指導を受けたボクらの前後4世代くらいは「お前達を写真で食っていけるようにする」という方針で指導された。
当時はモノクロ写真だけであったが現像、焼付、パネル貼りまでの製作工程はもとより、撮影技術、時にモチーフに対するアプローチの姿勢なども指導を受けた。クラブの顧問というより、どこかの写真家の工房に弟子入りしたような雰囲気だった。だからほとんどのメンバーは〈写真の道〉で生計を立てることになる。ボクのように公務員になったものは少数派で肩身が狭い。
ボクは写真をうまく撮ることが上手ではなく、在学中も後輩たちが道展(北海道主催の文化展)や各種カメラ雑誌やコンテストに入選するのを横目に、下級生にレギュラーポジションを奪われた上級生の悲哀を味わっていた。
写真で食べていく道は選ばなかったが、写真や映画、そして絵画など視覚芸術文化に対する興味の土壌はここらへんで形成された。
SNSの時代ではあるがボクはFacebookしかやっていないので、今の「インスタ映え」というのがピンとこなかったがフォトジェニックとほぼ同義といわれれば納得である。正確にいえば海外ではフォトジェニックは人に関しての「写真映え」。主に美男美女の映画スターの顔立ちに関してフォトジェニックという言い方が一般的であった。現在、わが国では風景や食べ物も含め、「インスタ映え」といえば、ビビットな色合いの変化をフォトレタッチ技術でさらに派手にした状態というのがボクの解釈。
山に登っても花や鳥、風景やありとあらゆるもので気になるものは写真に撮るので、連れの歩行ペーストと合わなくなる。そもそも連れの方がペースが早いのに、さらにこちらが遅れると待たせ困らせることになる。一方〈写真を撮る〉ということが疲れた時の口実になるので、ボクにとっては様々な意味で助けになる。
フォトジェニックな山
燕岳は花崗岩で形成された山で、山頂周辺は白い岩石が露出して山全体が色白の美人のような、優しくて美しい印象の山だ。
この山はフォトジェニックな山である。山そのものだけでなく、周りもフォトジェニックにする山だ。人気の山小屋・燕山荘も山の風景に溶け込んでフォトジェニック。秋の紅葉と常緑樹や山容が織りなす絶景。ライチョウの生息地であり、日本の雷鳥は人間にいじめられた経験が薄いようであまり逃げないのでとてもフォトジェニックな野鳥である。ちなみに欧米でクリスマスの時期に食べる七面鳥は、以前は雷鳥だったらしく、ヨーロッパの雷鳥は人間を見たらすぐ逃げるそうだ。北海道にもエゾライチョウという別種の雷鳥がいるが、これはきわめて美味な狩猟鳥で、とても用心深い。
燕岳がフォトジェニックなのはもう一つ理由がある。人間のポートレートを撮る時、レフ板という反射板を使って下から光を当てると、とてもフォトジェニックな写真が撮れる。テレビの女性アナウンサーをよく下からライトを当てて、見栄え良く映している。燕岳の白い花崗岩で山頂全体が天気のいい時はフォトスタジオみたいな状態である。だから登山者は誰でもフォトジェニックな記念写真が撮れる。
この燕岳から常念岳、大天井岳、蝶ヶ岳に続く登山道は〈北アルプスの表銀座〉と言われている。銀座とつくぐらいなのでフォトジェニックな場所なのである。このルートから眺める槍、穂高の山並みや遠望する富士山や麓の田園風景など、まことに美しくその景色を堪能しながら稜線を優雅な気分で歩くことができる。
ボクたちは蝶ヶ岳から下山し、豊科のマチに降りた。このエリアは山岳写真家で高山蝶の撮影でも有名な田淵行男氏のフィールドで、豊科には「田淵行男資料館」がある。連れ合いが『黄色いテント』(山と渓谷社刊)というエッセイ集を読んでいた。また、テレビ番組のドラマでもその活動が紹介されていた。ボクの両親の故郷・知床の斜里町には串田孫一が創刊した『アルプ』という山岳文芸雑誌の資料を集めた「アルプ美術館」という私設美術館がある。ボクたちのお気に入りの美術館で何度も訪れている。そこで田淵氏の高山蝶のスケッチを見ることができた。そんな縁も含めてフォトジェニックな山行であった。
現在のボクは、観ることに関しては写真より絵画の人であるが、カラバッジョの明暗法(キアロ・スクーロは著名な映画撮影者であるヴィットリオ・ストラーロも映画撮影に取り入れている)、フェルメールのカメラ・オブスクラ(初期のカメラを自らの絵画表現に取り入れた)、ダ・ヴィンチのスフマート(重ね塗りで輪郭線を描かない技法で空気遠近法と呼ばれたりする)などは、その後の写真や映像文化につながる技術的アプローチである。
ボクはロイスダールが描いたオランダの「雲」やターナーの絵画における「空気感」などが紡ぎ出す「気象」にも惹かれる。
日々刻々と変化する山の自然に抱かれながらの山行は、ビジュアルとピクチャレスクな両面を味わいながら、岩稜の散策路を歩いている趣で、我ながら贅沢な楽しみ方だと思うのである。

いつでもどこでも北アルプスから富士 
信じられない燕山荘のケーキバイキング 
常念手前の常念小屋が今日の宿 
お楽しみの夕食、結構な賑わい 
ハンバーグだよ~~ん 
ちょっと霧のなかの常念岳山頂 
蝶が岳に到着、高山蝶の棲む山々 
下山中みつけたゴジラの樹、結構有名だそうです 
クロマメノキの紅葉と背後に黒部峡谷が空気遠近法