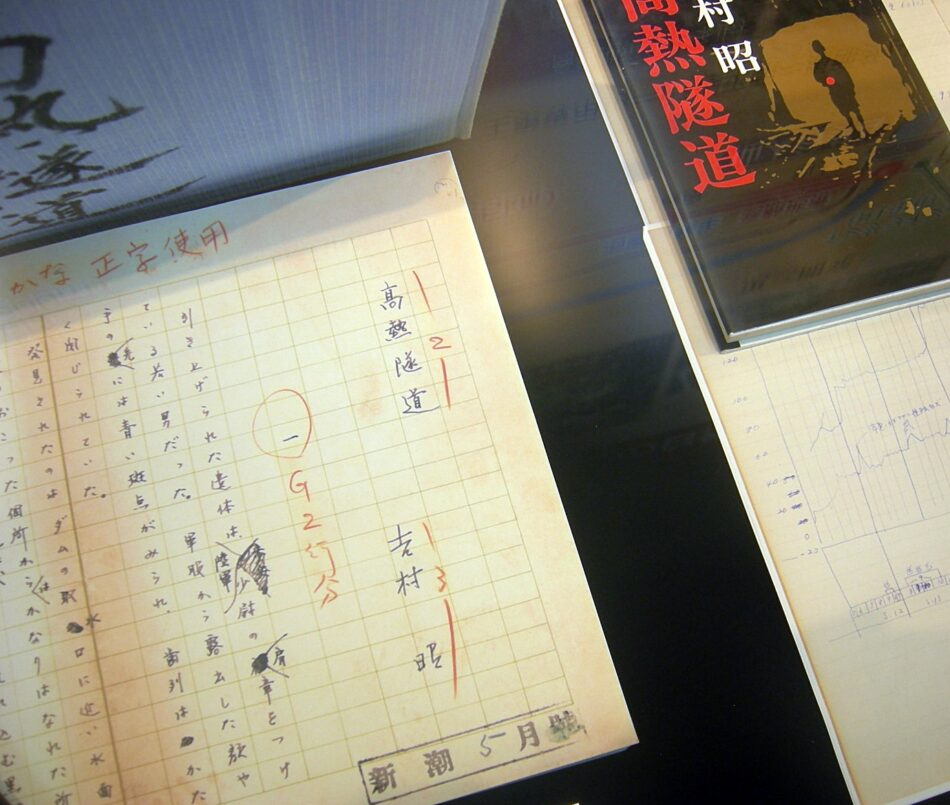2017年4月6日~17日
英国(湖水地方、コッツウォルズ、ロンド ン)
アナロジカルな旅
アナロジー( Analogy 類推・類比 )という言葉を初めて知ったのは佐藤優の著書だったような気がする。グローバル時代にあって課題解決のために同じような問題を抱えている地域を比較検討し、その類似点から解決への方向性を探る試み。
著名な作曲家と懇談する機会があった。阿寒湖畔の前田一歩園三代目店主・前田光子の話をした。創設者・前田正名の意思を受け継ぎ、阿寒の森の保全とアイヌを含む地域社会の人々と自然の共生に向けて尽力した光子は、「阿寒のハポ(母)」として今も敬愛される。
話を聞いた作曲家は英国のビアトリクス・ポターの話をボクにしてくれ、是非一度、湖水地方に行ってみて、とアドバイスをくれた。ピーターラビットは連れが全集を持っていて、家の中にもコーヒーカップや食器に、以前は風呂の桶までピーターラビットが描かたものがあり、身近な存在であった。しかし、その作者のことはとんと知らず。ビアトリクス・ポターと前田光子の共通点を調べることは単なる雑学を超えて阿寒の観光振興策についてのヒントを与えてくれるのではないか、という期待が生まれた。
『ミス・ポター』(クリス・ヌーン監督 レネー・ゼルウィガー主演)という映画も公開されていて、少しずつポターや湖水地方の情報や知識は膨らんでいった。しかし時間とお金に余裕のない阿寒湖温泉生活の間、湖水地方を訪問する夢は実現せず先送りのままであった。その間、観光客の入り込みは長期低落傾向を続け、一方で従来の温泉地として新たな魅力の掘り起こしに地域は苦慮していた。他と違う観光地としての差別化や自然の魅力を観光資源としていかす方法等々。それはボク流にいえば新たな〈旅文化〉を探る試みであった。
阿寒の仲間と「阿寒クラシックトレイル」という探検家・松浦武四郎や先人たちが歩いた古道を探訪するルート開発もその具体的な試みのひとつであった。
戦後日本の観光文化は一言で言えば「るるぶ(泊まる・食べる・遊ぶ)」に集約されるかもしれない。しかし多様性にあふれたグローバル社会にあって、競争原理に巻き込まれないオンリーワンの魅力づくりは、阿寒湖温泉という地域社会の持続可能性のために必須のものとなりつつあった。
市役所を退職し、阿寒湖温泉を離れ、釧路で自然ガイドを始めてから4年目。やっと湖水地方を訪れることができた。
旅のテーマは、アナロジカルな視点で阿寒湖温泉と湖水地方を考えることと、イギリスのフットパスで歩く観光を考えることの2点であった。
ネット時代の旅
ボクたちの旅は基本的には個人旅行なので、すべては個人で手配することになる。インターネット時代の変化を最も痛感したのはこの旅行であった。飛行機や宿泊ホテルの手配はこれまでも「トラベルコちゃん」や「ブッキング・コム(Booking.com)」「エクスペディア(Expedia)」などを使って国内旅行と変わらない感覚でスケジュールを組んでいた。しかし、この旅はフットパスを歩きながら移動するため、接続する交通機関は地域の路線バスや鉄道であった。またフットパスの地図や所要時間などの情報も必要であった。結果的にこれらはすべてインターネットで情報提供されていた。なんとイギリスのパブリック・フットパスは全てではないだろうがほぼ網羅されているデジタルデータがネット上で公開されている。
さらに驚くべきは地域の路線バスの走行ルートと時刻表(これは必ずしも正確とは言えない部分もあったが)もちょっとした英語力があれば調べることができた。ボクたちはまだスマホユーザーではなかったので、これらの情報は必要な箇所をプリントアウトして持参したがスマホを使えばもっと楽チン。バス料金の支払いもガード決済で出来た。
また、地球が狭くなったことを実感もした。アジアの極東の地・釧路からイギリスまで、1日で行くことができることをご存知だろうか。
我々は午前1時に起床し、2時に釧路を自家用車で出発。新千歳空港から韓国仁川空港経由の大韓航空でヒースロー空港に着き、国内線を乗り継ぎ、マンチェスターに到着したのはその日の午後10時であった。つまり8時間の時差オマケつきの1日32時間で目的地に着いた。
旅はイギリスの労働者が「歩く権利 Right of way 」を獲得したマンチェスターからスタートし、1日目はウインダミア湖を中心とする湖水地方周辺を現地のネイチャーガイドの案内で全体を把握。2日目は湖上を渡り対岸のビアトリクス・ポターがトラストで保全したヒルトップを見学しバスを乗り継ぎワーズワースが暮らしたグラスミア湖周辺のフットパスを散策した。
翌日は湖上遊覧でウインダミア湖南端から蒸気機関車に乗るアトラクションに参加。その後、湖水地方を離れコッツウォルズ地方のフットパスを散策するためチェルトナムまで列車で移動。ここからフットパスを歩きながらバスを乗り継ぎコッツウォルズ・ウェイと呼ばれる164km に及ぶ代表的なフットパスの部分を虫食い的に歩きながら終点のチョッピング・カムデンという街まで2泊3日歩いた。
好天に恵まれ春の草花やバードウォッチングを楽しみながら、イギリス人の〈歩く文化〉の一端を感じることができた。その後、我々はロンドンで2日間過ごした。ロンドンにはテムズ川沿いにテムズパスといわれるフットパスがあるが、我々は街歩き観光と美術館巡りで楽しいイギリス旅行の締めを堪能した。

国鳥コマドリはあちらこちらで 
1日の元気の源はイングリッシュブレックファースト 
移動の路線バスには2階建てもあり 
世界一美しい村バイブリー。住民に無断侵入の観光客が怒られていた 
柵を越えてフットパスは続く 
変わった入口、小さなサインが頼り 
ブロードウェイタワーに向かって牧場を歩く、羊の群れに出会うのも魅力
歩くことの意味
この旅は阿寒の観光振興の行方やボクのネイチャーガイドとしての方向性、そして旅文化そのものについて多くの示唆に富んだ旅となった。阿寒の観光振興については、機会があったらとおもい準備をしているのだが、今現在、声はかからない。老いたるは出しゃばるなを旨としているので、これは機会がある時に。
旅から帰ってしばらくしてから歩くことの意味についてとても参考になる一冊の本に出会った『誰も知らなかった英国流ウォーキングの秘密』(市村操一著 山と渓谷社)である。
イギリスのウォーキング文化について我々も歩いた現地を紹介しながら、散歩する権利についての歴史的な紹介や日本のウォーキングについての考察など、とても興味深いテーマが記されていた。
特に著者が「歩くことの意味」を10のウォーキング・スタイルに類型化し整理していることが興味深かった。①思索の― ②宗教的― ③自然観照― ④達成への― ⑤訓練の― ⑥余暇活動としての― ⑦コミュニケーションのための―⑧教育的― ⑨見せる― ⑩健康のための― である。自分を例にとれば毎日の散歩は①と⑩で連れと一緒の場合は加えて⑦である。登山は③④がメインだが振り返ると①⑤も…。お客様をガイドする時は⑧だがお客様の様子に合わせて①や③も意識する。
ボクにとっての「観光振興」とは観光資源の掘り起こしであり、発見であり、それを享受する術である。市役所の観光部門に勤めていた時もネイチャーガイドとして仕事をしている現在も基本的には変わらない。その基本をボクは〈歩く〉という移動の原点に探し続けているように思う。だから〈歩く〉ことの意味を考えることは、ボクの〈旅文化〉そのものを見つめ直す契機にもなる。
湖水地方にあって、阿寒に無かったものは何か?
ボクは④自然観照のウォーキングに注目した。「観照」は「鑑賞」とは違い、「静かな心で自然に向かい、その本質を見ようとする態度」(同著より)という意味である。詩人ワーズワースが愛したグラスミア湖のフットパスや芭蕉が歩いた奥の細道のような、自然と対話し自分を見つめる散策。与えられる教育的観察ではなく、自然の本質を散策者自らが探究する態度である。
「自然は偉大なる師なり」(前田光子)という謙虚な態度で自然と対峙した前田光子の心と重なるウォーキングルートが阿寒にもっとあっていいのではとおもう。現在も「光の森」があるが、もっと開放されて多くの人に「観照」を楽しんでほしいとおもう。
阿寒クラシックトレイルをボクはどんなおもいで始めたのか? 仲間や参加者たちはそこにどんな思いを持っていたのか? この10の類型化をモデルに考えてみるとそれは一つではなく、きっと複数の組み合わせで作られているように思う。そこに「観照」の視点はあったのか?
「るるぶ」に集約される旅文化が多様性を帯び、グローバルな人の交流とインターネット時代の情報交換により変貌していく。「文化とは歴史的に形成された外面的および内面的な生活様式のシステムでありグループの全員もしくは特定の成員によって共有されているもの」(哲学事典平凡社)という文化の解釈に従えば、コロナ禍のなか、新たな生活様式が求められる現在、我々の〈旅文化〉も必然的に見直しを迫られる時を迎えている。
〈歩くことの意味〉を通して、そのことを〈歩きながら=旅しながら〉考え続けて行きたいとおもう。

街角でウォーカーにエール 
アン・ハサウェイの家にて 
ロンドン3連泊の安宿B&B 
宮殿庭園でバードウォッチング 
ナショナルギャラリー無料で名画鑑賞 
コートールド美術館でマネの傑作と 
コッツウォルズ・ウェイを次の街に向かって牧場の中を歩きます